歌の上達に大切な3つの力
大好きな曲と出会う。
歌ってみたくて仕方がなくなる。
毎日聴く。何度も聴く。
そして、一緒に口ずさむ。
鼻歌で歌う。
覚えたらカラオケ屋さんに行って、その曲を歌ったりもする。
これが一般に「歌が好き」と言われる人の、
一番多い行動パターンでしょう。
実際に歌を志すなら、もう一歩前に進みたい。
誰でもやることをやっているだけでは、
人より前に出ることは出来ません。
「歌の上達に大切な力」は3つ。
1.歌の魅力を細部まで分析できる力
2.カラダの細部とつながって、表現する力
3.自分の歌を的確にジャッジする力
「好き」というのと「魅力がわかる」というのは、
イコールとは限りません。
魅力を完璧に理解できたからといって、
実際に自分自身がそれを表現できるかどうかは、
全く別の次元のお話です。
歌の魅力を十分理解した上で、
自分自身がそれを的確に表現する。
自分のパフォーマンスを細部まで、
きちん、きちんと理解、分析する。
歌い出しから、音の切り、間まで、すべてに責任を持つ。
これ、実は、料理で考えるとわかりやすい。
あるレストランでご馳走になって、
「美味しい!」と感動した料理があるとしましょう。
美味しくて、美味しくて、何度も食べに出かける。
時々マネしてつくってもみる。
でも、自分の料理ではイマイチ感動できなくて、
また食べに出かける。
これは、誰でもやること。
一歩進むには、
どうしてそのお店で食べると美味しいのかを
徹底的に分析、考えることです。
材料が違うのか。
調味料が違うのか。
調味料の分量が違うのか。
調理器具が違うのか。
火加減が違うのか。
お皿やお店の雰囲気なのか。
そのすべてが「料理人の腕」ということになります。
「料理好きのお客さん」ではなく、
「腕のいい料理人」を目差すなら、
分析したデータを元に、
自分自身で何度も試行錯誤しながら、
それを再現できなくてはいけない。
本当にその料理の魅力を完璧に表現できているのか、
冷静に味わって、フィードバックしながら、
料理の腕を磨いていかなくてはいけない。
何度食事に出かけても、
どれだけ料理に一家言持っていようとも、
お客さんはお客さん。
「送り手」になるには、
それなりの覚悟と準備が必要なのです。
◆【第5期 MTL ヴォイス&ヴォーカル レッスン12】 受講受付中!
関連記事
-
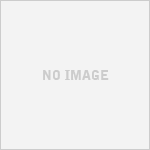
-
話を聞かない生徒 話をさせない先生
「これは、こんな風に歌うのよ」と、 お手本を聴かせるためにこちらが歌い出した瞬間 …
-

-
「ツボ」をはずした練習は、単なる自己満足であり、時間の無駄。
実は私、とっても足が遅いのです。 いきなり、しかもB面で何を言い出 …
-

-
歌がうまくなる“地獄聴き”のススメ
歌がうまくなりたくて、がんばっているのに──どうにも伸び悩んでいる気がする──。 …
-

-
「知ってる」だけで「わかった気」にならない。
「知識欲」こそが「学び」の基本。 「知りたい!」という気持ちが湧かなければ、 あ …
-

-
聞いてるつもり。できてるつもり。がんばってるつもり。
「え?ホントにそんな風に聞こえるの? なんでそんな風に聞こえるかなぁ・・・・」 …
-

-
やっぱ、英語なんだよなぁ。
日本語の歌を歌っているとめちゃくちゃカッコいいのに、 英語の歌になったとたんに、 …
-

-
英語の歌詞を覚える最終手段は“映像化”と“体感”
「三つ子の魂百まで」というけれど、思春期に捕らわれた思いこそが人生を左右するんじ …
-

-
「送り手」になりたかったら、「受け手」と同じことをしていたのではダメです。
「歌が好きだから、毎日歌っているんですよ」という人は、たくさんいます。 毎週のよ …
-

-
人間がカラダをつかってやることの基礎って、すべて同じなんだ。
うん十年ぶりにスキーというものに出かけてきました。 ぶっちゃけ、学生時代に友だち …
-

-
「限界ギリギリの定番曲」をいきなり歌う。
練習はルーティンからはじめる、というのは、 どんなスポーツでもおなじではないでし …
- PREV
- 音楽をどうやって聴くか?
- NEXT
- 自分にない価値観を学ぶのが学習ってもんだ

