無駄な力を抜く!〜そんな筋肉つかいません!〜
「力を抜いて!」
「リラックスして!」
「力まないで!」
このことばを、一日のレッスンの中で、一体全体何回言うでしょう?
そのくらい、力が抜けない、力んでしまうことで、
パフォーマンスが上がらないシンガーが多いと言うことです。
この『声出していこうっ!』はボイトレブログなので、
あえて「シンガー」と限定しましたが、
力みグセや、リラックスできないことで、本領が発揮できないのは、
どんなパフォーマンスでも同じでしょう。
というか、この世の中に、力むこと、リラックスしないようにすることで、
うまく行くことってあるのでしょうか?
全身で力んでいるかのように見える重量挙げでさえ、
特定の筋肉がMAXの力を発揮するためには、
不要な力は抜かなくてはならないはずです。
人間にとって、「力を抜く」というのは、実に大切なことなのです。
では、なぜ、そんなに大切なことを、
こんなにもできない人がたくさんいるのでしょう?
そもそも、力む、すなわち、筋肉に力が入るということは、
「スイッチON」の状態です。
死んだ人間は完全に脱力していますよね?
人間は生きているからこそ、脳から、
何かしらの電気信号のようなものが流れ、筋肉が緊張し、力が入る。
力が入れられるということは、力は抜けるはずなのです。
ところがです。
人は力を入れることよりも、抜くことの方が苦手です。
意識的に力を入れている場所でさえ、
脱力することが難しい人もいるくらいですから、
無意識に入っている力においては、
どうやっても抜けないという人がたくさんいます。
ポイントは、まず、力が入ってしまっていることに気づくことです。
どこの筋肉にどのくらい力が入っていて、それはどんなときに起こっているのか。
歌ったり、話したりするときに、
肩が上がる。
肩や首が前に出る。
顔がこわばる。
顎が開かない・・・などなど。
中には、なにもしていないときも、肩が上がっている、
奥歯を噛みしめている、顔をしかめている・・・などという人もいます。
まずは気づく。
そして常に、自分の筋肉の状態をチェックして、
力が入る瞬間を捉え、気づくたびに力を抜く練習をしてみましょう。
なにか動作をしようとするときに、
不要な筋肉に力が入ってしまう癖を取るには、
スローモーションでその動作をしてみて、
力が入る瞬間にがくんと力を落とす練習をすることです。
例えば、力をぐっと入れないと、
高い声が出ないとか、
大きい声が出ないとか、
滑舌がくっきりしないという人がいますが、
すべて勘違いによる、フォームの乱れです。
高い声や大きい声を出す筋肉はカラダの外部にはありません。
一度、アウターマッスルに力を入れて高い声や大きい声を出すことを覚えてしまうと、
そうした声を出そうとした瞬間に、反射的に、ぐっと力が入ることになります。
アウターマッスルが力むほどに、反対に声域は狭まっているのですが、
力を入れないと出ない気がして不安になるのです。
まずは思い切って、脱力したまま、さまざまな声を出すコツをつかんでみましょう。
声を育てるのは、うまく脱力ができてからです。
いかがでしょう?
まずは、自分の力みグセを探してみてくださいね。
関連記事
-

-
カラダと仲直りする。
“30 Days of yoga”というYoutubeの …
-

-
風邪の治りかけ。「ガラガラ声」の原因は?
今年の風邪はいやらしい、とは聞いていましたが、 いやいや。まじで。 いつまでも、 …
-
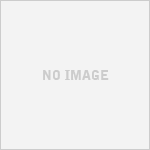
-
ボイトレにストレッチって、必要ですか?
ボイトレをはじめると、必ずと言っていいほどやらされるのがストレッチです。 やれ「 …
-

-
マスクは「声」をダメにする!?
先日、新宿駅を歩いていたときのこと。 背後でおしゃべりしている若い女性たちの声を …
-
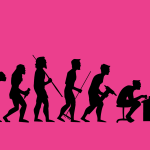
-
退化か?最適化か?顔筋がなくなる日。
この秋から、新たに、新人グループの育成を担当しています。 高校生から20代前半の …
-

-
「死ぬほどへたに歌う」をやってみる
世界中の人が、来る日も来る日も、 次から次へと流れこんでくるニュースに胸を痛め、 …
-

-
いつもベストな状態でパフォーマンスしたいなら
声の調子が悪いというと、のど飴をなめる。 目の調子が悪いといえば、目薬をつける。 …
-
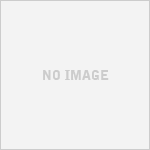
-
声帯さまってすごいんです
声帯ってどんなものか知っていますか? 声にトラブルを持ってお医者さんに行ったとい …
-

-
自分の「サイズ」に合った声を出す
管楽器ほど、 一目見ただけで音色の想像がつく楽器もないでしょう。 大きさ通り、見 …
-

-
カムバックを狙え!
足を骨折したことがあるでしょうか? ギブスにすっぽりと守られて、 まったく動かせ …
- PREV
- 「歌の表現力」ってなんだ?
- NEXT
- 「自分だったらどうか」という視点で考える

