先人たちの名演に学ぶ
ボーカリストにとって、いや、ミュージシャンにとって、
最高の教材は先人たちの残してくれた名演の数々です。
ライブ録音はともかく、きちんとレコーディングされたものは、
(もちろん、録音された時代や音楽の種類にもよるので、一概には言えませんが、
少なくとも、ここ20年〜30年くらいのポピュラー音楽では)
ちょっとしたニュアンスや、節回しさえ、
繰り返しレコーディングされたものの中のベストテイクです。
デモの段階から、歌唱やプレイを練りに練る人もいるでしょうし、
プリプロから、本番まで、何十トラックも録音して、
どんな表現がベストか、なんども試行錯誤するアーティストもいます。
だから、たとえば歌い出しの音の入り方ひとつ取っても・・・
ぽ〜んと一瞬で音を捕らえて、即座に減衰するように歌い出すのか、
子音を強調して、アタックをきかせてからぐいんと伸びるように歌うのか、
ラップ調に、思いきりビート感で攻めるのか、
フェードインするのか、
はたまたズリ上げるのか・・・すべて意味があることなのです。
そんな名演と言われるものには、
ワンフレーズにさえも、信じられないくらいたくさんの情報が詰まっています。
ダイナミクスのつけ方。
間の取り方。
音色。
ニュアンスのつけ方。
声のエフェクターの使い方。
音の入り方。止め方。ことばの発音の仕方。
グルーブの感じ方。。。。
真似をはじめたとき、すぐに歌えた気になるのは、
こんな情報がまったく拾えていないから。
そして、たいがいの人が、それで満足して終わってしまいます。
でも、歌のプロを目差す人は、それではダメなんです。
情報が拾えないということは、表現できないということ。
表現したいと思うこともない。
表現したいのに、テクニックが追いつかないことに気づくこともない。
これでは上達しないし、伝わりません。
大好きなアーティストの歌を真似てみる。
徹底的に真似てみる。
すると、なぜ、そのアーティストの歌が魅力的なのかがわかる。
なぜ、自分の歌が面白くないのかが、わかる。
それがやっとスタートラインです。
「モノマネとかって、好きじゃなくって。オリジナリティ大事にしたくて」
そんな声が聞こえます。
表現できる絵の具もことばも持たないまま、
ただただ、必死に、自分の手持ちの表現に感情をぶつけて、
相手にわかってもらおうと期待することがオリジナリティでしょうか?
それはボキャブラリーの乏しい、子供のおしゃべりと同じです。
それはオリジナリティというのではなく、「稚拙」というのです。
真似するくらいで消えてなくなるようなオリジナリティなら、とっとと捨てましょう。
関連記事
-
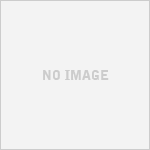
-
上達と進歩は一瞬でやってくる!
どんなに練習しても、ちっともうまくならない・・・ そんな時はだれだって、心が折れ …
-
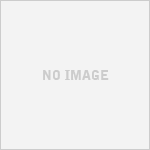
-
「仕事に困らないミュージシャン」の3つの特性
仕事がなくなると、景気だの、時代だのと世の中のせいにしたがるのは、 ミュージシャ …
-

-
プロフェッショナルの徹底ピアノ調整!
10月末から1週間ほど休業&家を留守にするということで、 思い切って、ピアノの一 …
-
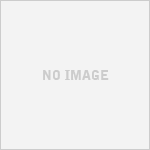
-
「こんちくしょうっ!」はチャンスの証
結果が出せない、大きな失敗をした、 彼氏(彼女)にふられた、人に認められない、陰 …
-
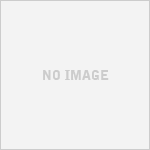
-
反面教師という大切な存在
「こんなピッチの悪い歌をわざわざ持ってきて、人に聴いてくださいって言える神経がわ …
-
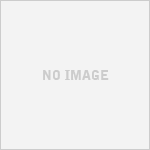
-
解剖学の本から『笑筋』が消える日?
うまく笑えない子が増えている。 「にっこり笑って」と言われて、前歯をきらりと見せ …
-
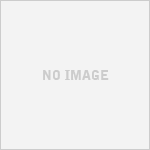
-
1年前の、1年後の自分との距離感。
1年という時間はあきれるほど速く流れて行きます。 その速度は生きた年月に比例して …
-
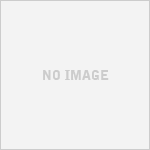
-
「お前よぉ、いい気になれよ」
かつてツアーのお仕事をした男性タレントのアンディーさん(仮名)が、 打ち上げの席 …
-

-
ミュージシャンに向いている人って?
「ミュージシャンに向いている人ってどんな人ですか?」 そんな質問を時々受けると、 …
-
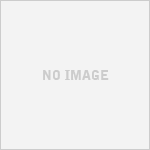
-
「そんなの歌ってても売れない」!?
時々、不思議な質問を受けます。 先日のキャサリン(仮名)の質問がまさにそれ。 「 …
- PREV
- 技術によって人間は進歩するのか、退化するのか?
- NEXT
- 「からだレベル」でグルーブを感じる
