話を聞かない生徒 話をさせない先生
2015/12/20
「これは、こんな風に歌うのよ」と、
お手本を聴かせるためにこちらが歌い出した瞬間、
こちらの声にかぶせて、一緒に歌い出す生徒というのがいます。
はじめは、「たまたまかぶっちゃったのね」、
「あ、今、聴くところってわかってないんだ」と、こちらもスルーするのですが、
毎回、毎回、「じゃあ聴いて」と言っているにもかかわらず、一緒に歌い出す。
聴く耳を持たないのは、感性が鈍い証拠です。学習の進行も当然遅い。
何回か続くと(続かなくても)、さすがにこちらもイラッとするので、
「ちょっと、聴いててっ!」と鋭く叱ります。
一般的には、先生と言われる人がお手本を聴かせようと歌い出したら、
口をつぐんで耳を傾けるのが常識です。
目の前でお手本を見せてくれるのですから、
耳だけでなく、五感を使って、全身全霊を込めて、
先生のやることを、見て、聴いて、感じて、盗まなくてはいけない。
そんな子に限って、話をしても、どこか上の空で心に響いている様子がない。
人が話しているのに、途中で自分の話にすり替えてしまうことさえあります。
「あなたは私の話が聞きたいの?それとも自分の話がしたいのっ!?」
そう、シャウトしたこともありました。
聴く耳を持たないというのは、情報に対し、またはコミュニケーションに対し、
心が閉じている証拠です。
自分の価値や、認識、知覚の範囲内だけで、理解できる情報以外は、
すべてシャットアウトしてしまう。
これでは、成長も拡大もあり得ません。
いや。ちょっと待って。
これって、生徒だけのお話でしょうか?
トレーナーも長くなるほどに、手癖や、習慣でレッスンをするようになりがちです。
自分の価値観、認識の範囲内だけで、生徒たちの状況を切り取り、
おきまりのアドバイスを繰り返すようになる。
生徒たちの言葉に、歌に、きちんと耳を澄ましているか?
生徒たちが発する情報を、「自分の常識」という色眼鏡をかけることなく、
素直な気持ちで受け止め、その価値観を理解しようとしているか?
こどもたちが先生の話を聞けないのは、家庭環境、すなわち育ちの問題です。
先生がこどもたちの話を聞けないのは、感性の老化です。
前者は、教える方が忍耐を持って訓練すれば正すことができますが、
後者は、自分で気づかなければ、誰も教えてくれません。
教わる方も教える方も、一生勉強です。
じっと胸に手を当てる夕べです。
関連記事
-

-
記憶に残る「デキるやつら」は一体何が違ったのか?
かつて、教えていた音楽学校では、ヴォーカルの授業を 定期的にインスト科の生徒たち …
-

-
「センスが悪い」と言われる人への5つのアドバイス
今日は昨日のブログの続きとして、 テクニックはあるのに、音楽的に評価されない、 …
-

-
練習を「単なる時間の無駄」で終わらせないための3つのポイント。
歌を志すことになったのは、 私にとって、ある種の「挫折」でした。 そんなことを言 …
-

-
「学び」はカラダに刻め。
生まれてはじめて、”8ビート”ということばを意識したのは …
-

-
「マネをする」という選択も、自分のオリジナリティの一部なんだ。
人に習うと、自分のスタイルが確立できないとか、 人のマネをすると、オリジナリティ …
-

-
思い込みと勘違いで他人に意見するのは一種の迷惑行為。
何年か前、知り合いの女性ヴォーカリストに、 「私、衣装は全部ネットで買っているわ …
-

-
「歌の練習」って、なにしたらいいんですか?
「練習って、なにしたらいいんですか? MISUMIさんは、なにしてるんですか?」 …
-

-
個人レッスン?グループレッスン?メリットと選び方
実によくされる質問のひとつに、 「個人レッスンとグループレッスンっだったら、やっ …
-
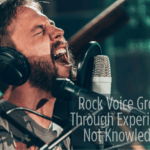
-
ロックな声は、“知識”じゃなく“体感”で育てる
ロックと言えば、バッキーンと突き抜ける高音。 そして、ハスキーボイス。 昨今、さ …
-

-
「自分らしさ」、一回置いておきません?
どんなヴォーカルスタイルが「自分らしい」んだろう? 「自分らしい声」って、どんな …
- PREV
- 歌の構成要素を分解する〜ラララで歌う〜
- NEXT
- 声の老化は隠せない
