頑固な、間違ったプログラムを解除して、「声」を解放する
カラダの構造や、発声のメカニズムを教えて、左脳からアプローチしても、
カラダに触れたり、一緒にストレッチしたり、筋トレしたりして、
右脳からアプローチしても、
録音させたり、歌い聞かせたりして、聴覚から訴えても、
チューナーの針や音楽ソフトなどの波形を見せて、視覚から訴えても、
ノドを触ったり、口の中を舌で触れたりと、触覚から訴えても、
「ここも、ここも、いいとこ、いっぱいあるじゃな〜い?」とホメ倒しても、
「ったくぅ〜!どうしてもっと真剣に取り組めないの〜〜!!!???」と脅かしても・・・
なかなか、なかなか、
思ったような気持ちのいい声が出てこない子というのがいるものです。
こんなとき、多くのトレーナーが、本人に聞こえないところで、
(時に、面と向かって言ってしまうツワモノもいますが)
このようなことを言います。
「そもそも、歌うような声じゃないのよね・・・」
私自身も、駆け出しの頃は、
相手の身体的な能力の原因ではないかと、ずいぶん疑ったものですから、
そう言ってしまう人たちの気持ちもわからないではありません。
しかし、ここでもう一度、
本の中で、ブログで、セミナーや講演会で、
何回言ってきたかわからないことばを繰り返します。
声のこもったイヌなんかいない。
声の枯れやすいライオンもいない。
神様は完璧なカラダをくれている。
完璧じゃないのは、カラダじゃなくて、持ち主のせい。。。
ただただ、
人間の脳は、長年繰り返している動作を正しいと思うようにつくられている。
そして、長年聞いている、自分自身の声を、
同じように出し続けるようにプログラムされている。
その頑固な、間違ったプログラムを解除できない限り、
人はなかなか、一皮むけない、というわけです。
そして、多くの、「不器用」な人たちは、
この、プログラムをどうやっても自分で解除できず、苦しむのです。
ところが、実に思いがけないくらい簡単な方法で、
この自動プログラムを、一時的に止め、
自分自身の気づかなかった自分の声の可能性に気がつくことができます。
それが、「イメージ物まね法」。
自分自身の声を、意識的にああ変えよう、こう変えようとするのではなく、
別人の声をイメージして、物まねして、声を出すのです。
「秋川さんのように声出してみて」
「体重100キロくらい太ったみたいな気持ちで声出してみて」
「聖子ちゃんみたいに歌ってみて」
そんな一言で、一瞬にして、びっくりするほど声が響くようになったり、
ぱき〜んと気持ちよく抜けるような声が出るようになったりします。
もちろん、誰かのマネをしたりして、無理な発声を続けることは、
発声器官に負担をかけますので、いいことではないでしょう。
しかし、ここでの目的は、自分自身が思い込んでいる
「自分の声」というイメージから離れて、
自由にカラダに反応させること。
イメージを変えると、カラダはそれまでの「思い込みプログラム」から解放されます。
そして、新しいカラダの感覚を目覚めさせる。
自分の中から新しい感覚を目覚めさせることを恐れてはいけません。
そのために、一時的にノドに負担がかかっても、大きな問題ではありません。
新しい筋感覚を取り出してから、整えて行けばいいのです。
いかがでしょう?
ぜひ一度、「イメージ物まね法」、試して、
自分の声の可能性を探してみてください。
人間のカラダは、実に驚異的に柔軟につくられているのだということに、
驚くかもしれません。
関連記事
-

-
歌詞が覚えられないのは、意味をわかっていないから。
「歌詞って、覚えられないんですよね。 どうしても、カンペ貼っちゃうんですよ。」 …
-

-
精度の高い”フォルティッシモ”を持て!
ダイナミクス、すなわち音量の強弱のコントロールが 音楽表現の大切な要素であるとい …
-
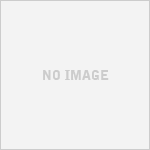
-
「怖いですかね?私?」
販売関係のお仕事で管理職を務める若き女性、Wさん。 「私、『もっと怖い人なのかと …
-

-
間違えるなら大胆に間違える。
ここ数日、あまり慣れないことに取り組んでいます。 慣れないことに取り組んでいると …
-

-
「本を読もう!」
「本読んでる?」 なんだか国語が通じないなぁ、と感じる生徒に出会うと、 思わず言 …
-

-
声の変化の分岐点を探す
今日のA面ではダイエットの話を書きました。 自分のカラダの変化の分岐点を見つける …
-

-
リズムが悪いのは「背骨が硬い」から?
音楽学校などでバンド・アンサンブルの指導をしていると、 一所懸命演奏する若者たち …
-

-
ギターの「早弾き」 vs. ボーカルの「高い音」
ボイトレというと、高い音ばかり練習している人がいます。 実際に、スクールなどでも …
-

-
キー設定にこだわり抜く
「キー、D♭でお願いします」 そんなことを言って、いい顔をしてくれるのは打楽器と …
-

-
「あの人、ノド大丈夫かな?」
仕事柄、お芝居やミュージカルなど、さまざまな舞台にお招きいただきます。 レッスン …

