まずオケを聴け!歌うのはそれからだ!
カラオケ文化というものが浸透してからか、
若手ヴォーカリストは、とにかくすぐに歌いたがります。
音源を聞くのは、曲を覚えるためだと思っているのではないかという疑惑さえ湧きます。
ちょこちょこっと1〜2回聴いたら、
いきなり歌詞カードを見ながら一緒に歌い出す。
カバー曲はもちろんですが、
新曲でも、一昔前のように、
作曲家の先生に譜面で曲を渡される、というようなことはまずありません。
たいがいが、ある程度完成しているカラオケに、
「仮歌」というお手本の歌が入ったデモ音源を渡されます。
なので、やはり、いきなり歌い出すわけです。
だからというのではないでしょうが、みんな曲を覚えるのは速い。
あっという間に「カラオケで歌う準備OK!」となります。
しかしです。
まぁ、細部の甘いこと。
メロディが曖昧。
ピッチがあまい。
リズムの縦が楽器とそろわない。
歌詞のハマりがところどころ適当。
音の長さがバラバラ。。。
それはそうでしょう。
ほとんど聴かないで、自分が一緒に歌っちゃってる訳ですから。
そして、そういうことに気づかず、「歌ってみて」というと、
気分良さそうに歌い倒す子のなんと多いことか。
カラオケ病とでも言うのでしょうか。
曲を覚えられて、高い声さえちゃんと出て、
歌詞を噛まなければ、ちゃんと歌えていると思ってしまう。
う〜ん。
音楽の聴き方の意識から変える必要がある子たちが、
いやはや、実にたくさんいるのです。
カラオケなど存在しなかった時代は、バンドと一緒に歌うしかありませんでした。
目の前でドラムがドンタンドドタンとやる。
ギターがじゃら〜んと弾く。
なんか違うなぁ。覚えている曲と全然違うなぁ・・・。
そんな風に思うから、またオリジナルを聴く。
バンドに指示を出す。
反対もありました。
「お前さぁ、あそこメロ違うよ」
「全然リズムハマってないじゃん」
バンドは、そうやってコミュニケーションを取りながら、
お互いにダメ出ししながら、上達したものです。
お互いの音を聞くことなしに、演奏は成立しなかったのです。
へたくそなバンド・メンバーにイライラすることなく、
完璧に近いオケで歌える時代が来たのに、
なぜ全体の歌のクオリティはちっとも上がらないのかといえば、
結局、元の音源も、自分が歌うオケも、ちゃんと聞いていないからなのです。
オケに含まれている音には、どんな音にも「理由」があります。
無駄な音は一音もないはずです。
歌もののオケならその歌を最大限に生かすための仕掛けが、
そこかしこにちりばめられているはず。
そのオケと心を一つにして歌う。
オケが歌を引き立て、歌がオケをさらに素晴らしく響かせる。
というわけで、今日は声を大にして言わせていただきたい。
「まずオケを聴け!歌うのはそれからだ!」
関連記事
-

-
「機材がない」を言い訳にしない。
時折、アーティストの卵たちや、学生たちに、宿題を出します。 その時 …
-

-
「完璧なパフォーマンス」ができても、「蚊の鳴くような声」じゃ、やっぱりダメなのよね。
ずいぶん前のことになります。 あの子、歌がめっちゃ上手いんですよ〜。 素晴らしい …
-

-
「向いてない」って、なんだよ?
つい数日前、はじめて訪れた耳鼻科の先生に、 「この声帯の形からすると、あなた、 …
-

-
「圧倒的な安心感」をくれるプレイヤーの条件
魅力的なプレイヤーたちとのパフォーマンスはドキドキ感の連続です。 心地よい音色と …
-

-
「そんなピッチで気持ち悪いと思わない自分をなんとかした方がいいよ」
「ああ〜〜、やめてぇ〜〜、気持ち悪いぃ〜〜〜っ」 音楽がなんとなくわかった気にな …
-

-
そのオリジナル曲、イケてる?イケてない?
オリジナル曲を人に聞いてもらうときには、 曲自体のクオリティ、構成などはもちろん …
-

-
「ツボ」をはずした練習は、単なる自己満足であり、時間の無駄。
実は私、とっても足が遅いのです。 いきなり、しかもB面で何を言い出 …
-

-
「練習しなくちゃ」と思ってしまう時点で、 ダメなんです。
「やらなくちゃいけないってわかっているんですけど、なかなかできなくて・・・」 & …
-
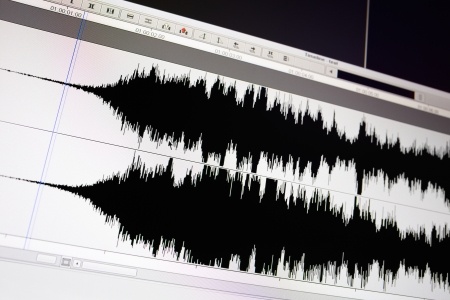
-
上達しないアマチュアに共通のマインド
最短で歌や楽器を上達する方法として、 多くのスーパープロが勧めるのは、完全コピー …
-

-
あなたのパフォーマンス、「政治家の謝罪会見」や「大根役者」になってませんか?
声の表現力について説明するとき、必ずやって見せる、 「政治家の謝罪会見」と「大根 …


Comment
>へたくそなバンド・メンバーにイライラすることなく、
> 完璧に近いオケで歌える時代が来たのに、
>なぜ全体の歌のクオリティはちっとも上がらないのかといえば、
>
>結局、元の音源も、自分が歌うオケも、ちゃんと聞いていないからなのです。
この指摘、否定しません。
しかし、それ以前に「歌とは何ぞや?」「音楽とはなんぞや?」をわかっていないからなのでは????
「音源を聴く、オケを聴く」と言われても、「聴き方」がわかっていなければ、100回聴いても無駄でしょう。
「聴き方」っていうのも曖昧な言い方であって・・・・・「音楽とはどのように成り立っているか?」って言った方がいいかもしれません。「アレンジとは何ぞや」という捉え方もできるかもしれません。
そういう知識がなければ、「どこをどう聴くの????」となるのは自然なこと。
リズムとは何のためにあるのか?ドラムにベースが乗って「リズム隊」と言われるのはなぜか?ベースはどんな機能を果たしているのか?キーボードやギターの役割とは?「伴奏」とはどういう意味か?・・・・・・等々。
「詞」だって、「想いを言葉にしたもの」レベルで理解している人だと、例えば「単語がメロディーにフィットするように選ばれている」なんていう捉え方はできないでしょうから、「詞の中身を味わう」はできても、技術的な意味での「聴き方」や「歌い方」はわからないでしょうね。
音楽は「感性、感覚」という側面もありますが、「計算して組み立てられている」という「理屈、理論」の側面もあるわけで、超一流のアレンジがなされた曲は、音楽理論の集合体だったりします。
こうした「知識」がなければ、たとえ聴いていても、押さえるべきポイントを逃してしまう。
私は、その昔、日本のトップクラスのバンドメンバーの方に基本事項を教えてもらったことで、多少「聴き方」がわかるようになりました。
だから「まず聴くということをしないのは問題」という指摘の意味がわかります。
「聴け!」の前に、ある程度の基本的な理屈を教えて「聴き方」を理解させてあげることも必要と思うわけです。
大切な人を、大切にしてください。
それが光なのだと思います。
p.s. わたしはKanだけ.