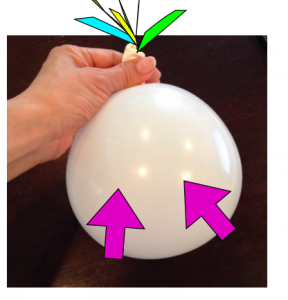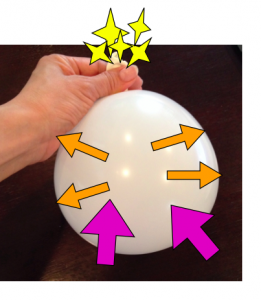めんどくさいけど大事な「呼吸の話」その2
2016/07/10
さて、前回お話しした呼吸の話のつづきです。
今日もマニアックにお届けします(^^)
初めての方は、7月14日の投稿、『めんどくさいけど大事な「呼吸の話」』を先に読んでくださいね。
肺は風船と同じだとお話しました。
当然、上下だけでなく、前後左右にも広がります。
下に広がるときに活躍するのが、前回お話した「横隔膜」。
そして、前後左右に広がるときに活躍するのが、今日ご紹介する「肋間筋」です。
肋骨はカゴのようなもので、がちゃんと固定されていると考えている人、
とても多いのですが・・・さて?
実は、肋骨=あばら骨は、背骨と胸骨にぶら下がっている、バラバラの骨。
この骨の間に、肋間筋という筋肉があって、胸の中のスペースを広げたり、狭めたりします。
(実際には内肋間筋、外肋間筋と2種類あるんですよ。マニアな方。念のため。)
この肋間筋が広がる力が、よく耳にする「声のささえ」をつくってくれるのです。
原理は至ってシンプルです。
横隔膜が上がるとき、肺を下から上にぎゅっと押し上げると、
息はどどっと一気に出てしまいます。
ちょうど風船の出口を絞った部分にあたる、
声帯さまに、思いきり、強い呼気をぶつけることになります。
これでは、声はコントロールできません。
声帯さまに負担もかかる。
息も続かない。
いいことなしデス。
どんなに大きな声、高い声を出すときも、横隔膜を一気に絞り上げるのではなく、
優しく、コントロールしながら上げることはもちろん重要なことなのですが・・・
横隔膜と同じくらい大活躍するのが、肋間筋。
肋骨の間の筋肉が、えいっと踏ん張って、
肋骨を開き、胸を広げようとし続けることで、
呼吸はほどよい圧力、量、スピードを保つことができ、
呼吸のクオリティは黄金になるのです。
まとめです。
歌う時のみならず、いい声を保とうとするときに大切なのは・・・
1下っ腹周辺筋肉を上手につかって、横隔膜の上がるスピードをコントロールすること。2.肋骨をしっかりと開いた状態に保つこと。
この2点は鉄板です。
原理はわかったけど、じゃあ、どうやってやればいいの?
・・・というお話はまた今度!
関連記事
-

-
歌っちゃいけない時。
私のレッスンでは、声出しの真っ最中に、「今日は、もうやめようか」と、レッスンをい …
-

-
「お腹は凹ますのか?突き出すのか?」問題について語ってみた
「歌うときは、おへその下10~15㎝下を少~しずつ凹ませましょう。 このとき、肋 …
-

-
痰がからむ声の不調、あきらめない!回復のステップ|18万PV記事の2025年最新版
コロナにかかってからノドの調子が戻らない。 ひどい風邪で声が出なくなって、何ヶ月 …
-
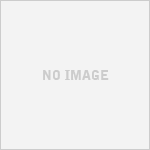
-
めんどくさいけど大事な「呼吸の話」
今日はちょっとマニアックに呼吸のお話をしましょう。 肺はあばら骨の中いっぱい、左 …
-

-
飲み会で声が枯れる理由
昨日お仕事納め、そこから忘年会だったという方も、 たくさんいらっしゃるのではない …
-

-
カムバックを狙え!
足を骨折したことがあるでしょうか? ギブスにすっぽりと守られて、 まったく動かせ …
-
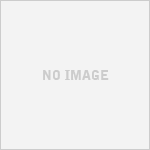
-
声帯さまってすごいんです
声帯ってどんなものか知っていますか? 声にトラブルを持ってお医者さんに行ったとい …
-

-
歌をはじめる黄金期?
歌をはじめるのに、 早すぎることも、遅すぎることもない。 これは私の持論でありま …
-

-
昭和音楽大学で、姿勢と呼吸を熱く語ってきました
昭和音楽大学で特別講義をしてきました。 テーマは姿勢と呼吸。 11月に大学のショ …
-

-
仕事中毒=「超人病」が、カラダと心を破壊する
ワーカホリック。 日本語で言うと、仕事中毒。 常に仕事をしていないと、または、そ …
- PREV
- めんどくさいけど大事な「呼吸の話」
- NEXT
- 「話すためのボイトレって、何するんですか?」