人を感動させる力の秘密は”HOW”じゃなく、”WHY”にある。
ピカソやゴッホをお手本に、
「この青は何番をつかって」
「ここの線はくっきり描いて」
などと解釈、解説をすることは、
ある程度、勉強をした人なら、
そう難しいことではないでしょう。
さらに自らも技術を磨けば、
限りなくオリジナルに近い、
線や色を描くことも、
不可能なことではありません。
世の中に出回っている模写や贋作は、
そんな職人たちの、
「技の極致」とも言えるわけです。
歌もおなじです。
このシンガーは、ここをこう歌って、
こっちは、こんな声を出して・・・と、
分析、解析する力は、
技術力を高めたいシンガーには必須の力であり、
歌を指導する立場にある人にとって、
それらすべてを言語化したり、
お手本として聞かせられたりできることは、
絶対条件であるとも言えます。
さらに、オリジナルのフレーズをなぞったり、
そっくりの声を出したり…
いわゆる完コピの精度をあげることで、
技術力、表現力が磨かれて、
プロの世界で認められるようになった人も、
洋の東西を問わず、星の数ほどいます。
私自身、そうやって技術を身につけ、
お仕事をいただくようになりました。
しかしね。
アートでも、音楽でも、歌でも、
本っ当に大事なのは、
HOW(どうやるか)じゃなく、
WHY(なぜ、それをしたのか)。
どうやって、その色を出したのか、
その線を描いたのか、じゃない。
どうやって、その声を出したのか、
そのフレーズを歌えたのか、じゃない。
なぜ、その色を選んだのか。
なぜ、そう歌いたかったのか。
これに尽きるんです。
この発想が欠落していると、
一生、本物の絵は描けない。
本物の歌は歌えません。
本物の職人にも、なれないでしょう。
なぜ、その被写体を、
その構図で、その服で、描きたかったのか。
なぜ、その筆と、その色と、その素材を選んだのか。
なぜ、その光を、なぜ、その表現を、選んだのか。
もちろん、アーティストの真意は絶対にわかりません。
たとえ、言語化されている情報が残っていたとしても、
そこに、彼らのパッションを見ることは不可能です。
しかし、それでも、
その「なぜ」に想いを馳せる。
「なぜ」に宿る、
人を感動させる力の秘密に想いを馳せる。
本物の「自分の表現」は、
そこを越えた先にあります。
モノマネ・レベルのことをやっていたんではダメなんです。
かといって、人の表現をなぞることを恐れてもダメ。
自分が自分であるために、最高の表現を選び取れる力を磨く。
そんな、本物の修行を、したいものです。

◆一生に一度、集中的に学ぶだけで、”自分で自分に教えること”を可能にするMTL 12。
毎週日曜日10時〜Youtubeにて公開中。
◆無料メルマガ『声出していこうっ』。バックナンバーも読めます。
関連記事
-

-
「カッコいいもの」と、それ以外
音楽学校などで、 「この曲を練習してきて」と課題曲を渡すと、 「この通り歌わなく …
-

-
「ライブのダメ出し」のタイミング?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2015年11月2 …
-

-
ホンモノか?ニセモノか?
「あいつはホンモノだよ」 「なんか、あの子、ウソくさいのよね」 一般の人たちがど …
-

-
行動しないで成功できる「成功法則」なんかないっ!
夢を叶えたいと思う人なら、 誰でも一度くらいは、 「成功法則」や「引き寄せの法則 …
-

-
人は、人を「育てる」ことはできない。
レッスンを担当しているシンガーたちが、 ぐんぐん成長していく姿を見るのは、誰だっ …
-

-
自分のリソースを「棚卸し」してみる
前か、後ろか、はたまた上か・・・ 先が見えなくて、身動きが取れないときは、 自分 …
-

-
「真っ白な灰」に、なりますか?
リングの上で真っ白な灰になった、『あしたのジョー』。 命を賭けられるほどのものに …
-
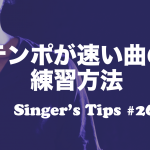
-
テンポが速い曲の練習方法~Singer’s Tips #26~
「ゆっくり目の曲はうまく歌えないんです。 テンポの速い曲の方が得意です。」 時々 …
-

-
「自分らしさ」を見出す3つの方法。
自分らしさや、自分の「売り」を探すとき、 頭の中で、ああでもない、こうでもないと …
-

-
「この辺でちゃんと仕事に就こうかなと思ってるんですけど・・・」
「MISUMIさん、俺、この辺でちゃんと仕事に就こうかなと思ってるんですけど・・ …
