「お腹は凹ますのか?突き出すのか?」問題について語ってみた
「歌うときは、おへその下10~15㎝下を少~しずつ凹ませましょう。
このとき、肋骨はできるだけ広げたままをキープして。」
MTLが指導する、「歌う呼吸法」です。
歌やヴォイトレを複数の先生について習った経験のある方は、
多かれ少なかれ、
この呼吸法の説明のバリエーションの多さに、混乱を覚えます。
「え?意識するのはお尻の穴って習ったんですけど・・・」
「お腹って、声出すとき、突き出すんじゃないんですか?」
「息をお腹で深く吸い込めって言われてきました・・・」
え〜〜っと・・・
まず、すべてのヴォーカルトレーナーの方たちの名誉のために申し上げれば、
感覚的な説明をする場合、正解はひとつではありません。
歌うときの呼吸の感覚は、
ヴォーカリストの数だけあると言っても過言ではない。
例えば、箸の正しい使い方を説明するのに、
どこの指に神経を集中させて、
どこに力を入れて、という感覚を言語化すれば、
10人が10人、違う説明をするでしょう。
自分にとって、結果を出せた方法が、自分の正解。
これが、「伝承」の難しさであり、奥の深さでもあります。
「え〜〜!!??そんないい加減なぁ・・・
じゃ、なに信じたらいいか、わかんないじゃないですかぁ〜〜・・・」
と読者の方が一斉にディする声が聞こえました(^^)
ご安心ください。
感覚はいろいろで、
だから教え方もいろいろなんですが、
何万年も進化していない人間のカラダにとって、
歌うときに最も効率のいい呼吸というのは、ひとつしかありません。
一定の量の空気を、
一定のスピードで、
コンスタントに出し続けられること。
必要に応じて、圧力の微調整こそあれ、
基本は、あくまでも、
「一定」「コンスタント」そして、もちろん「省エネ」です。
さて。
大きな風船の中にたくさんの空気を入れて、
空気の出口を軽〜く閉じて、
その出口が(風船の吸い口のところですね)
いい感じにぶるぶるぶるっと振動するように、
一定に、いい感じの量の空気を、
なるべく長い時間出し続けられるようにするには、
さて、どうしたらいいでしょう?
風船の方を押さなければ、
空気は全く出ませんから、当然振動も起きません。
つまり、声も出ません。
だから、どこかを押すわけです。
この際、上部を押そうが、下部を押そうが、
関係ありませんね。
空気は外に出ようとします。
しかし、ただガ〜ッと押してしまえば、
空気の量も圧力もスピードもコントロールすることはできません。
一気に空気はなくなってしまいます。
風船の吸い口も、
いい感じの振動どころか、
ぶぴぴぴぴぴぴっとものすごい音を立てて、
最後は一気にブハッと空気を外に出そうとするでしょう。
そこで、この、押しだそうとする力と拮抗する力が必要になるわけです。
ここで、風船が形状記憶だと想像してください。
つまり、押そうとする力に風船そのものが抵抗します。
その2つの力が空気の量やスピード、圧力を一定に保つのです。
人間のカラダに話を戻しましょう。
押し出そうとする力は、
コントロールが容易かつ、力強くなくてはいけません。
たくさんの呼吸を扱うことを考えれば、
可動域が広いことも大切です。
その役割を担うのは、
骨盤低筋群、腹横筋などの下腹部の腹筋群です。
「お尻の穴」と考えた方が下腹部の腹筋を意識しやすいのか、
「おへそ」と考えた方が意識しやすいのかは、
人によって違うのは前述のとおりです。
私のように、「愛の歌を歌うときに、お尻の穴のことを考えたくない」という人もいるでしょう。
最初に意識するポイントは、どうあれ、
お腹を使っていくのは下から上。
下腹部を徐々に締め上げていくイメージなのです。
その際に、形状記憶の役割をするのが、肋間筋、
すなわち、肋骨のまわりの筋肉です。
下腹部の力で空気が押し出されようとするときに、
肋骨が形状を保とうとすることで、
空気の量、スピード、そして圧力が一定に保たれるわけです。
この、肋骨を外側に押しだす、と言う感覚を
「お腹を膨らませる」と感じる人もいるということです。
いかがでしょうか?
呼吸法は無酸素運動をする人たちにとっても、
エアロビクス、ヨガやピラティスなど、
有酸素運動をする人たちにとっても、
悩ましい問題です。
しかし、人間のカラダにとっての真実は、
何万年も変わっていません。
どんな風に感じるのが自分にとって一番しっくりくるのか。
さまざまな情報を取り入れた上で、
正解を探すのは、結局、自分自身なのですね。
購読はこちらから。
関連記事
-

-
「聞こえませーん」
会議の時、 「聞こえませーん」と言われることが恐怖で、 必死に声を振り絞って話す …
-

-
あがり症を克服する3つの方法
ビジネスボイトレを受講する人には、「あがり症」を訴える人が少なからずいます。 「 …
-

-
ネックの曲がったギター vs. 姿勢の悪いヴォーカリスト
姿勢やフォームが悪いヴォーカリストは、 ネックの曲がったギターに例えるのがもっと …
-
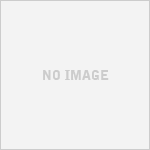
-
声のクオリティを上げる!
あちこちで、最初の一声で「つかむ」ことの大切さを書いてきました。 それでも、話を …
-

-
ハスキーボイスには2通りある
ハスキーボイスといわれるシンガーは、その発声の特徴によって、 実は2通りに分かれ …
-

-
声が自分の顔になる。
小学校の高学年の時、流行の「深夜放送」というのを聞いてみたくて、 ゲルマラジオと …
-

-
声のリハビリ
3月からのライブ・ラッシュに向けて、 朝トレをしているわけですが、 ここ半年あま …
-

-
頭痛がイタい!?
ここ1~2週間、頭痛に悩まされていました。 毎朝、首がぱんぱんに張って目が覚める …
-

-
カラダという楽器 〜 Singer’s Tips #9 〜
ピアノでも、ギターでも、 「さぁ、弾こう」という前に、 弾き手が必ずするのがチュ …
-

-
「自分の音域を知らない」なんて、意味わからないわけです。
プロのヴォーカリストというのに、 「音域はどこからどこまで?」 という質問に答え …
- PREV
- 「自然体」を演出する。
- NEXT
- 「カッコいいやつ」が「カッコいいやつ」と呼ばれる5つの理由

